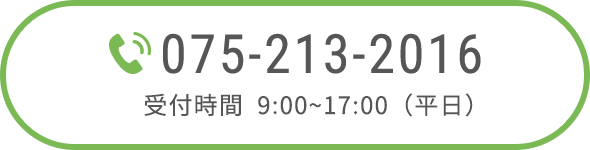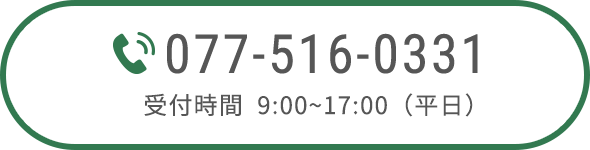☆供託を利用した休眠担保権抹消登記の手続について☆
こんにちは。今回は供託を利用した休眠担保権の抹消登記申請について記載させて頂きます。備忘録としての意味合いが強いため、少し専門的な内容となっておりますがご了承下さいませ。
さて、供託を利用した休眠担保権の抹消登記申請とはどのような制度なのかを説明させて頂きます。それにはまず、担保権の抹消登記申請の基本から。担保権の代表的なものに抵当権がありますが、抵当権の登記を抹消する際には、抵当権者と抵当権が付いている不動産の所有者が2人で共同して登記申請をする必要があります。しかし、昔のご先祖様が抵当権を設定されて時間が経っていると、不動産の相続人が登記簿を見て抵当権が付いているのを発見し、当該抵当権の登記を抹消しようと思っても、抵当権者が誰なのかさえ分からないといった事象が生じます。その場合、抵当権者と一緒に抵当権抹消登記申請をしようと思っても難しいですよね。そこで、不動産登記法には、抵当権の抹消登記を単独でできる場合の一つとして、供託を利用した俗にいう休眠担保権の抹消の制度を用意してくれております(不動産登記法第70条第4項後段)。
要件としては、①抵当権者が所在不明、②被担保債権の弁済期から20年、③その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭を供託となります。
よって、これらの要件を証する書面を収集し、抵当権抹消登記申請を不動産の所有者が単独でしていくこととなります。
【所在不明証明情報】
この制度は、抵当権者が所在不明の場合に利用することができますので、それを証明する書類が必要となります。①登記簿上の抵当権者の住所・氏名宛に郵送をして、「あて所に尋ねあたりません」と返送された封筒と、②登記簿上の住所での不在住証明書が必要となります。
郵送は、債権受領催告書なるものを封筒に入れ、配達証明付きで本人受取受取郵便、速達にて郵送致しました。
【弁済期の確認】
現在の不動産登記簿には弁済期は記載されていないのですが、コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本(昭和39年4月1日前のもの)には弁済期が記載されているため、閉鎖登記簿謄本を取得しました。古い謄本は手書きで達筆であるため、初めてなので読むのに苦労しましたが、法務局の方に丁寧にお教え頂きました。その節は誠にありがとうございました。記載内容は似たようなものが多いと思いますので今回の記載例を参考に挙げておきます。
(記載例)
弁済方法
大正〇〇年〇〇月〇〇日より同〇〇年〇〇月〇〇日まで
毎〇月、〇月、〇月 各〇日 1回金〇〇円 宛崩済(ほうさい)
【供託金額の計算】
債権額、利息及び損害金の全額を供託する必要があります。そうするとすごい金額になるように思われますが、大正時代の債権額は、何百円ということが多いですので、そこまで高額ならないことが多いと思います。
今回の案件では、債権額が500円でしたので、約4,000円でした。
抵当権者が準共有の場合は、債権額を人数で等分した金額でそれぞれ供託金額を計算します。
また、計算はソフト(権という登記申請用ソフト)を使用したのでとても楽でした。初期設定のまま、何回払いかを選択するだけで、すぐに作成できました。
自前でエクセルで作成する場合は当時の利息制限法を確認したり、利息や損害金を全て計算しないといけないので大変だと思われます。
【供託手続きの委任状の作成】
供託手続きのための委任状を作成します。委任状には今回の供託内容の詳細を記載した別紙と、上記の供託金額の計算書を袋とじにしたものを作成致しました。抵当権者が準共有であったため、それぞれ委任状を作成致しました。
ちなみに、委任状の日付は供託日を入れます。
【供託手続きの準備】
供託手続きにおいては、供託日をいつにするのかがとても重要です。日程がずれると、損害金の計算が変わってくるため、計算書や委任状を全て作りなおさないといけません。
お客様から委任状が返ってくるまでの期間も考慮に入れ、供託日を定め、その日までに準備を全て終わらす必要があります。
作成した供託申請書や供託金計算書が閉じられている委任状を事前に供託所へFAXし、計算間違いがないか等のチェックもして頂きます。
【供託の申請】
供託の申請は、ソフト(権という申請ソフト)を使用してオンラインで致しました。
供託申請書での記載についていくつか補足させて頂きます。
「供託通知書の発送を請求する」のチェックはしません。債権者所在不明なので送れないため。
「電子供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の発送を請求する」にチェックを入れると、電子供託書に加え、紙の供託書正本も送って頂けます。
「備考欄」に、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条第1項により端数処理。」と記載します。
オンライン申請後、添付書面を返信用封筒と一緒に供託所へ郵送致します。添付書面は委任状のみでした。弊所は法人なので、原則は履歴事項証明書も必要ですが、会社法人等番号を供託申請書に記載することで添付省略ができます。
添付書面が供託所へ届き審査が終わると、申請用ソフトの処理画面にて、納付の画面が閲覧できるようになるので、供託金を納付致します。
その後、同じく申請用ソフトの処理画面にて公文書の項目が確認できるようになり、ここらか電子供託書正本をダウンロードできます。当該電子供託書正本はそのまま抵当権抹消登記申請に使用していきます。
【抵当権抹消登記申請】
最後にようやく抵当権抹消登記申請を致します。
抵当権抹消登記の申請書の記載につき、いくつか補足をさせて頂きます。
登記の原因は、供託日ではなく、供託金の納付日を記載し、「年月日弁済」とします。
供託日までの損害金にて供託金額を計算し納付しているので、供託日が登記原因日付のような気がしないでもないのですが、登記手続上はこのような扱いとなっております。なので、抵当権抹消登記の委任状の日付も納付日以降になっていないといけないので注意が必要です。
添付書面といたしましては、①登記原因証明情報として、電子供託書正本及び弁済期を証する閉鎖登記簿謄本(原本還付処理)、②所在不明証明情報として、不到達であった封筒及び不在住証明書(どちらも原本還付処理)、③委任状を法務局へ提出致しました。
以上が、供託を利用した休眠担保権抹消登記の一連の流れとなります。
いかがだったでしょうか。
こちらのブログで少しでもお役に立つことができれば幸甚でございます。
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続・遺言専門サイト@優司法書士法人
優遊ブログ
みんなの家族信託